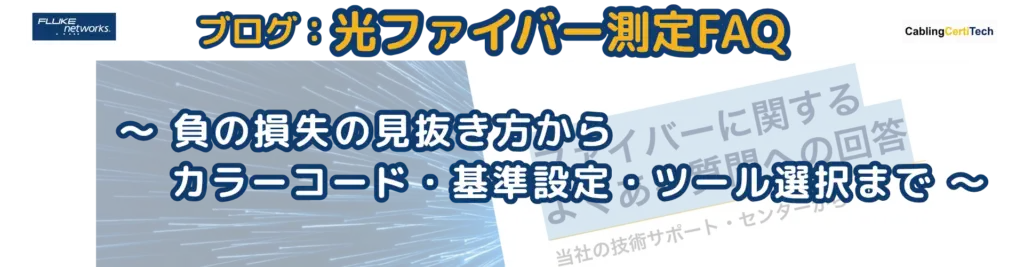
【注記】
本記事は、Fluke Networksのサポートを受け、同社の技術資料「ファイバーに関するよくある質問への回答」を基に、Cabling Cert Techが独自の視点で作成したものです。
はじめに:なぜ光ファイバー測定が重要なのか
データセンターや企業ネットワーク、そして5G通信など、あらゆる高速通信の根幹には光ファイバーがあります。
その性能を最大限に引き出すには、「正しく測る」ことが第一歩です。
測定値が正しくなければ、ネットワークがどれほど良い設計でも信頼できません。
この記事では、フルーク・ネットワークス社のFAQ資料をもとに、現場でよくある質問やトラブルをわかりやすく整理します。
損失バジェットの計算からレポートの読み方、端面クリーニング、そしてツール選びまで、“これだけは押さえておきたいポイント”をまとめました。
損失バジェットとは? ― 光信号がどれだけ減っていいかの目安
光ファイバーでは、信号は必ず少しずつ減衰します。
その「許される減衰量」の上限を 損失バジェット(Loss Budget) と呼びます。
計算式はシンプルです:
損失バジェット = (ファイバー長 × ファイバー損失) + (コネクター数 × コネクター損失) + (スプライス数 × スプライス損失)
例:OM5マルチモードファイバー(250 m, 4コネクター, 2スプライス)
- ファイバー損失:3.0 dB/km
- コネクター損失:0.75 dB
- スプライス損失:0.3 dB
→ 計算結果:(0.25×3.0) + (4×0.75) + (2×0.3) = 4.35 dB
この4.35 dBを超えると、規格上「不合格」となります。
CertiFiber™ ProのようなOLTS(光損失テスター)を使えば、コネクター数とスプライス数を入力するだけで自動計算されます。
テストレポートの見方 ― 合否マークだけで判断しない!
測定後に出力されるレポートは「配線の成績表」です。
ただし、“PASS(合格)”マークだけを見て安心するのは危険です。
次の3点を必ずチェックしてください。
✅ 1. テストリミットの確認
使用した基準が TIA/ISO規格 なのか、
それとも アプリケーション規格(例:40GBASE-SR4) なのかを確認します。
一部の業者が「合格に見せるため」に、実際より多いコネクター数を設定してリミットを緩くするケースもあるので要注意です。
⚠️ 2. 「負の損失(マイナス値)」は赤信号
損失値がマイナスになることは物理的にあり得ません。
これは 基準値設定(ゼロ点合わせ)を誤った ことを示しています。
たとえ他の値が正に見えても、すべて無効になる可能性があります。
→ この場合は 全測定をやり直すのが鉄則 です。
🔍 3. TRC(テスト基準コード)の品質チェック
正確な測定には、高品質なTRCを使った「1ジャンパー法」が推奨されています。
基準設定直後に表示されるTRCの損失値が、
- マルチモード:0.15 dB 以下
- シングルモード:0.25 dB 以下
であることを確認しましょう。
もし負値や過大な値が出たら、TRCを清掃・交換して再設定します。
ファイバーとコネクターのカラーコードを正しく理解しよう
光ファイバーは、種類を見分けるためにジャケットやコネクターの色が決められています。
誤った組み合わせは大きな損失の原因になります。
| カラー | 種類 | コア径 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| オレンジ | OM1 / OM2(旧仕様) | 62.5µm / 50µm | 低速・短距離 |
| グレー | OM2(現行多い) | 50µm | 混在防止用 |
| アクア | OM3 / OM4 | 50µm | 10G〜100G |
| ライムグリーン | OM5 | 50µm | SWDM対応 |
| イエロー | OS1a / OS2 | 9µm | シングルモード |
コネクター色(フェルール側)
- ブルー: シングルモード(UPC)
- グリーン: シングルモード(APC、斜め研磨)
- ベージュ/アクア: マルチモード用
👉 ポイント:アダプターの色もコネクターと合わせると誤接続防止になります。
クリーニングの基本 ― 「検査→乾式→湿式→再検査」
端面の汚れは、トラブルの約80%を占めます。
クリーニングの鉄則は、検査から始めて検査で終わること。
1️⃣ 検査:FiberInspector™などで端面をチェック。
2️⃣ 乾式クリーニング:クイッククリーナーを使用し、1回押し込みで清掃。
3️⃣ 湿式クリーニング:落ちない油分には、光ファイバー専用溶剤を少量使用(※アルコールはNG)。
4️⃣ 再検査:再度マイクロスコープで確認し、汚れや傷がないかをチェック。
トラブルシューティングツール ― 障害箇所を見つける3つの選択肢
| ツール | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| VFL(可視光源) | 近距離の割れ・屈曲確認 | 赤色レーザーで光漏れを目視 |
| Fiber QuickMap™ | ~1.5 kmまでの障害検出 | OTDRの原理で高損失点までの距離を特定 |
| OTDR | ティア2認証・詳細解析 | 反射波を分析してイベント位置と損失を数値化 |
まずVFLで目視、届かない場合はQuickMap、最終確認や報告書レベルの検証にはOTDR、という使い分けが効果的です。
まとめ:正確な測定がネットワークの信頼性を支える
- 損失バジェットは「どれだけ減っていいか」の基準。
- 負の損失は「再測定」のサイン。
- TRCと1ジャンパー基準を守ることが精度の鍵。
- 汚れは敵。必ず検査・清掃・再検査。
- 適切なツールで障害を素早く特定。
光ファイバー測定は、単なる「テスト作業」ではなく、ネットワーク品質を守る最後の砦です。
今日から、レポートの数字一つひとつに“理由”を持って判断できるエンジニアを目指しましょう。
📘 参考資料
Fluke Networks. FAQ: 光ファイバーの測定に関するよくある質問への回答.© Fluke Networks.
🔗 そして、最後に
このブログのベースになった 「ファイバーに関するよくある質問への回答」 は、以下のリンクからダウンロードいただけます。


